はじめに

お腹が痛い
——そう訴えたのが、すべての始まりでした。
3歳の末っ子が入院して、胆管膵管合流異常と診断されたときのことを、
同じように突然の入院に向き合う親御さんの参考になればと思い、記録として残します。
突然の診断。3歳で「胆管膵管合流異常」と言われて
ある日、保育園から「お腹が痛いみたいです」と呼び出しがありました。
かかりつけの小児科では「便秘ですね」と言われたものの、夜になって嘔吐をくり返し、再度受診。
「原因がわからないので、大きい病院へ紹介します」と言われ、
そこでのエコーと血液検査で胆管膵管合流異常が見つかりました。
「え、先天性なの?」「治すには手術しかないの?」
驚きよりも、どこか冷静に受け止めていた気がします。
先生からは「また症状をくり返す可能性があり、ゆくゆくは手術の必要もあるかもしれません」と説明を受けました。
入院期間は1〜2週間の予定が、結果的に12日間に。
私自身が切迫早産などで入院経験があったので、家族の反応も「また入院?」くらいで、意外と落ち着いていました。
持って行って助かったもの
まず思ったのは、「入院中に3歳がどう過ごすか」。
すぐに子ども用タブレットと着替え、オムツを準備しました。
時間を持て余すのが、いちばん大変だと思ったからです。
病院からもらった「入院のしおり」に基本的なものは載っていましたが、
やっぱり娯楽関係は自分で考えるしかないです。
子どもにとって“退屈”は敵です。

本が好きな子、YouTubeが好きな子など、子供によって好みも違いますもんね。
ポケットWi-Fi
一番助かったのは、ポケットWi-Fiです。
病棟のWi-Fiも使えましたが、90分ごとに再認証が必要で、3歳児には難しい…。
そこで使ったのが、楽天の
我が家は14日レンタルで1日10GBまで使える無制限プランにしました。
動画を見ても通信制限にかかることはなく、設定に関しても機械が苦手な私でもすぐにできました。
即日発送で、返却はポストに入れるだけ。
もし入院が伸びても、レンタル期間を延長できるのもありがたかったです。
病院のWi-Fiが混雑して遅くなることもあるので、こうした自前のネット環境があると本当に安心。
子どもが飽きずに過ごせるし、親も調べものや仕事をするのに助かりました。
タブレット
入院中はどうしても時間を持て余すので、子ども用タブレットは必須でした。
我が家ではAmazon Fire HD キッズモデルを使ってます。
もともと使い慣れていたので、末っ子も操作はお手の物。
このタブレットは、子ども向けの専用カバー付きで丈夫。
ベッドから落としても安心で、しかもAmazon Kids+ のコンテンツが1年間使い放題です。
アニメや知育ゲーム、絵本なども充実しているので、入院中でも飽きずに過ごせました。
画面サイズも10インチと大きく、ベッドの上でも見やすいです。
充電の持ちもよく、1日中使っても余裕でした。
本・ぬいぐるみ・ぬりえ
短期入院でも、本を数冊とお気に入りのぬいぐるみはあった方がいいです。
最初からぬいぐるみを持って行っていたので比較はできませんが、
家から持ってきた安心できるもの”があると、子どもも落ち着くように感じました。
病院によってはプレイルームや保育士さんもいますが、
慣れない環境の中では、自分のものがそばにあるだけで安心感が全然違うと思います。
また、静かに過ごせる時間のために塗り絵もおすすめです。
我が家では
を持って行きました。
どちらも専用ペンで描くタイプなので、テーブルやシーツを汚す心配がありません。
色が浮き出るように出てくる仕掛けに夢中で、病室で過ごす時間が少し楽しくなりました。
夜の付き添い

完全付き添いの病院ではなかったけど、「夜はきっと不安だろうな」と思って毎晩付き添ってました。
私が仕事終わって夕方に家へ帰って夕飯を準備 → 自分もお風呂 → すぐ病院へ。
売店の前で軽くご飯を食べて、いざ病棟へ。
子どものサークルベッドで一緒に寝るか、ソファベッドを使うスタイル
夜を一緒に過ごし、寝かしつけをして始発で帰る——。
そんな生活を1週間ほどしていました。
ほとんど眠れませんでしたが、
夜だけでもそばにいられることが、何よりの安心につながりました。
サークルベッドは小児用で、高さを変えられるのは柵の部分だけ。
ベッド自体の高さは変えられません。

私(156cm)でギリギリ足を伸ばして寝られるくらい。男性だと少しきついかもしれません。
昼間の過ごし方

保育士さんが常駐している病院だったので、プレイルームで過ごしたり、タブレットを見たり、車椅子でお散歩したり。
穏やかに過ごすようにしていたようです。
ただ、お風呂は大の苦手。
もともとお風呂嫌いなうえに「怖い」と感じることも多く、入浴の声かけをすると脱走してしまうことも。
体が元気になってくると、そういう抵抗も出てきました。
不安な気持ちへの寄り添い
入院中、末っ子は何度も「ママ大好き」と言ってくれました。
きっと、それは不安の裏返しだったんだと思います。
そのたびに「ママも大好き」と返すと、少し安心した表情を見せてくれました。
短いやり取りでも、気持ちはちゃんと伝わっていた気がします。

どうしても不安になると思うので、安心させることに注力しました。
一番つらかった瞬間

入院中にヒステリーを起こすと、もう手がつけられません。
何を言ってもダメ。暴れて散らかしたものを片付けようとするのも気に入らない。
ゴミ箱を倒して、自動ドアの前に置いておかないとまた泣き叫ぶ——。
落ち着くまで待つしかないけれど、その姿を見るたびに胸がぎゅっとなりました。
「ちゃんと産んであげられたら」「もっと自由に動ける仕事なら、ずっと付き添えたのに」
そんな気持ちが込み上げて、気づけば涙が出ていました。
退院前の3日間。小さな心の大爆発
退院が近づくにつれて、末っ子のヒステリーはどんどん激しくなっていきました。
脱走したり、泣き叫んだり。
たぶん、「体は元気なのに、なんでまだここにいるの?」という気持ちに加えて、
思いどおりにできないストレスが積み重なっていたんだと思います。
寝かしつけもしてくれないので昼寝もできず、好きなご飯も食べられない。
大好きなチョコも禁止で、おやつはゼリー1個だけ。

退院してからは、まるで反動のようにチョコを“これでもか!”というくらい食べていました。
小さな我慢が積もり積もって、最後の数日は大爆発。
退院が決まっても、本人はまったく理解していませんでした。
それだけ“病院で過ごす生活”が、すっかり日常になっていたんだと思います。
退院する日の朝。小躍りで病棟を出た日
退院のことは、直前に伝えました。

退院するよ

まだご飯食べてないよ?
と、最初はピンと来ていない様子。
でも、ベビーカーに荷物を積み始めた瞬間に何かを察したのか、パッと表情が明るくなって、
靴を履いてぴょんぴょんと小躍りしながら、会う人会う人に手を降って自動ドアを出ていきました。
その姿を見た瞬間、涙が滲みました。
「よく頑張ったね」「やっと帰れるね」
と思わず声をかけました。
退院後の生活
退院後、先生から言われたことは以下のとおりです。
- 腹痛があったらすぐ電話。
- 便秘薬はしばらく継続(腹痛があったときに、便秘の痛みかかわからないため)
- 油ものは控えめに。 「避けてほしいけど、年齢的に無理だと思うから程々に」と言われました。
- 運動制限なし。
- 保育園も登園OK。
実際、退院の翌日から保育園にも登園しています。
本人も先生に会えるのが嬉しかったようで、朝からウキウキで登園していきました。
家ではまだ夜中にヒステリーを起こすことがあり(夜泣きのような感じ)、
心が落ち着くまでにはもう少し時間がかかりそうです。
そして、正直なところ、親の方もかなり疲れが溜まっています。
ずっと張りつめたまま過ごしてきた反動が、今になってどっと来ている感じです。
でも、焦らずゆっくり。今はそれでいいと思っています。
無理に元のペースに戻そうとせず、“少しずつ笑顔が戻る日常”を大切にしていきたいです。

仕事や家事してたら、自然にもとのペースに戻っていました
同じように不安な親御さんへ
子どもの入院は、親にとっても試練のような時間です。
泣いたり、悩んだりしながらも、気づけば少しずつ、前を向けるようになっていきます。
無理をせず、焦らず、「今日を乗り切る」だけで十分です。
にほんブログ村
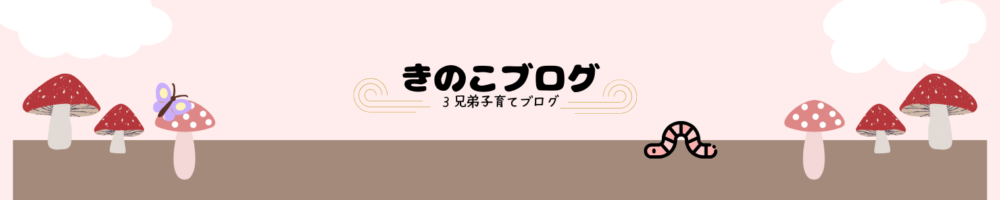

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d697fc1.32245e2d.4d697fc2.93f575f5/?me_id=1330172&item_id=10000237&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwifi-rental%2Fcabinet%2Fthu%2F10220454%2Fimgrc0096474710.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



コメント